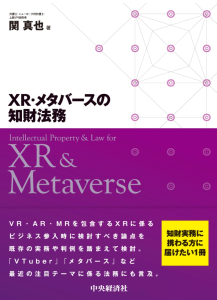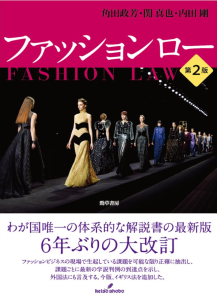概要
書籍の著者らが、大規模言語モデル『Llama』の学習データとして彼らの書籍を利用したMeta Platforms社(以下、メタ社)の行為につき著作権侵害を主張して提訴した事件で、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、2025年6月25日、当該行為はフェアユースに該当する(したがって著作権侵害は成立しない)との判断(サマリー・ジャッジメント)を示しました。
上記判断に関して裁判所が示した理由の要点をまとめると、概ね以下のようになります。
- フェアユースの第1要素(利用の目的及び性質):メタ社が原告らの書籍を利用したことが、当該書籍とは異なる目的及び性質を有し、高度に変容的(transformative)であったことは疑いようがない。メタ社による複製の目的は、多様なテキストを生成し、幅広い機能(例:ユーザーが書いたメールの編集、翻訳、シナリオに基づく寸劇の執筆など)を果たす革新的なツールであるLLMを訓練することであったのに対し、原告らの書籍の目的は、娯楽又は教育のために読まれることであった。
- フェアユースの第4要素(著作物の潜在的な市場又は価値に対する影響):Llamaは、原告らの書籍から50語を超える部分を再現することができないという制限が設けられていたため、Llamaが生成するテキストが原告らの書籍を代替することはできず、その潜在的な市場又は価値に有意又は重要な影響を及ぼすおそれはない。
- 同じく第4要素:多様なテキストを生成し、幅広い機能を果たすLLMを訓練するという変容的な目的のための著作物の利用に係るライセンス市場は、フェアユースの第4要素とは無関係である(変容的な利用であるにもかかわらず、著作権者がライセンス料の支払いを受けるべき正当なライセンス市場が存在することを前提にフェアユースの成否を判断してしまうと、第4要素の分析が循環的となり、すべてのケースにおいて著作権者に有利な判断になってしまう)。
このように、本判決は、結論としてフェアユース該当性を否定しました。
本判決が示した一般論
ー生成AIモデルの学習と著作権侵害ー
フェアユースの成立を認める一方で、本判決は、一般論として、生成AIモデルの学習のために無断で著作物を利用する行為につき、多くの場合に著作権侵害が成立し得ると述べています。
その根底には、次に引用するように、人間の創作活動のインセンティブを守るという著作権法の目的を最も重視し、これを損なう行為にフェアユースは適用されないという考え方があります。
フェアユースは、新しい技術とその潜在的な影響に対してセンシティブな、ケースバイケースの分析を要する具体的事実に即した法理である。LLMの訓練のように、変容性が高く、オリジナル作品の市場を希薄化させる可能性のある利用に関する事例は、過去の裁判例には存在しない。したがって、メタ社の複製がフェアユースに該当するかどうかという問いに答える裁判例はない。その問いは、フェアユースの要素を柔軟に適用し、メタ社の複製行為を著作権及びフェアユースの目的 —— すなわち、オリジナル作品の市場において代替する作品を複製者が作成することを防ぎ、創作のインセンティブを保護することするという目的 —— に照らして検討することによって答えなければならない。
著作物を無断で利用され、市場において不利益な取扱いを受けるような場合に、クリエイターの創作活動に対するインセンティブや意欲は損なわれます。このため、本判決は、その利用がいかに変容的であっても、著作物の市場等が著しく害される場合には、フェアユースの第1要素よりも第4要素を重視してフェアユースに該当しないという考え方を示したものと考えられます。
フェアユースに該当しない場合、他に理由がない限り著作権侵害が成立し、適法にその著作物を利用するためには著作権者にライセンス料を支払う必要があるため、クリエイターのインセンティブ(著作権法の目的)は守られることになります。
生成AIはなぜ市場を害するのか?
ー「市場の希釈化」を問題とすべき生成AIの特殊性ー
次に生じる疑問は、本判決はなぜ、生成AIモデルの訓練のために著作物を複製することが著作物の市場を害すると考えたのかという、フェアユースの第4要素に関する問題です。この問題に関し、本判決は、「市場の希釈化」という概念を強調しています。
この点、本判決の直前に出され、Anthropic社の対話型生成AI『Claude』を訓練するための書籍の複製につきフェアユース該当性を認めた判決(Bartz v. Anthropic PBC, No. C 24-05417 WHA (N.D. Cal. June 23, 2025))においてカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、LLMの訓練が著者らの作品と競合する作品の爆発的な増加を引き起こすという「著者らの主張は、学校児童に良い文章を書くように訓練することが競合する作品の爆発的増加を引き起こすという主張と何ら変わりない。これは、著作権法が懸念する競争的又は創造的な置換ではない。著作権法は、創作的な著作物の促進を目的とするのであり、著者を競争から保護するものではない」と述べています。
これは、生成AIの学習を人間の学習と変わりないものと捉え、人間が著作物を学習した結果として市場に競合作品(学習された原著作物と創作的表現と共通しないもの)が現れたとしても著作権侵害にはならないのと同様に、AI生成物が学習された著作物と市場において競合することは著作権侵害を肯定する理由にはならないとしているものと評価できます。
対話型生成AI『Claude』を訓練するための書籍の複製はフェアユースに当たる―米国連邦地裁が判断(関真也) – エキスパート – Yahoo!ニュース
この点に関する本判決の考え方は異なります。
まず、本判決は、生成AIモデルの学習に関する事案の特殊性を次のように述べ、「市場の希釈化」という問題をフェアユース(第4要素)の分析において検討すべき理由を説明しています。
たしかに、多くの著作権事件では、市場希薄化や間接的代替という概念は特段重要なものではない。これは、典型的なケースでは、オリジナル作品が単一の二次的作品と対比されるためである。二次的作品が多少類似しているものの、事実上複製とみなされるほど類似していない場合、その二次的作品はなおオリジナル作品の市場にわずかな間接的影響を与える可能性がある。・・・・・・類似してはいるがその程度は十分でない単一の二次的作品に関する場合、市場の希釈化による損害が問題となるほど重大になる可能性は低いであろう。
本件は事案が異なる。これは、オリジナル作品が単一の二次的作品と対比されるケースではない。・・・・・・本件は、学習に利用されたオリジナル作品を創作するために用いられた時間と創造性のごく一部だけで、文字通り数百万の二次的作品を生成することができる技術に関するものである。(単一の二次的作品の作成であろうと、他のデジタルツールの作成であろうと)他のいかなる利用も、競合作品を市場に氾濫させる可能性において、LLMの訓練には及びもつかない。したがって、市場の希釈化という概念が極めて重要となる。
また、本判決は、以下のとおり、前掲Bartz v. Anthropic PBC事件判決とは異なる考え方をとっています。
しかし、市場効果という点において、児童に書くことを教えるために書籍を使うことは、一人の個人が本来要する時間及び創造性のごく一部だけで無数の競合作品を生成することができる製品を作り出すために本を使うこととは、全く異なる。この不適切な類推は、フェアユースの分析において最も重要な要素を無視する根拠にはならない。
要するに、本判決の「市場の希釈化」に関する議論は、生成AIが、無数の競合作品をごく短時間で生成して市場に氾濫させることにより、人間が伝統的な方法で創作活動を行うインセンティブを損なうことを問題視しているのであり、一個人が競合作品を作り出すのとはわけが違うと言っているのです。 この「市場の希釈化」は、米国においては著作権局のレポートで分析されるなど検討が進んでいる考え方ですが、わが国では、(少なくとも創作的表現のレベルにおいて類似しないケースでは)著作権侵害を肯定する方向に評価されることは多くないようです。
加えて、本判決は、「LLMは、著作権で保護される書籍の創作的な表現を学習しているがゆえに、テキスト(競合作品を含む。)を生成する能力に優れている」(のであり、著作物の創作的表現から利益を得ているといえる)とも指摘しています。この点も、生成AIの学習と著作権に関するわが国の議論ではあまり指摘されておらず、注目に値するでしょう。
著作権者は何を立証すべきか?
以上のとおり、本判決は、生成AIモデルの学習に著作物を無断で利用するケースについて、「市場の希釈化」を立証することによりフェアユースの成立が否定され、著作権侵害が成立する可能性があるという一般論を示しました。
しかし、結論としては、その立証がなかったことを理由にフェアユースを認めました。
今後、生成AIモデルの学習に関する事案ではこの点の立証が重要な争点となる可能性があります。本判決は、著作権者が立証すべき事項として以下のような例を挙げており、参考になります。
- 書籍市場の分析(AI生成書籍が書籍市場に与える影響や同市場における競合の可能性など)
- 競合による書籍の売上に対する影響
- LLM開発者が原告らの書籍をコピーできる世界とコピーできない世界における書籍市場に対する脅威の差
まとめ
本判決は、AIモデルの生成物が、学習された著作物の創作的表現において共通しない場合においても、「市場の希釈化」による損害が著作権者に及ぶことが立証される限り、フェアユースが否定され著作権侵害が成立し得ることを示した点において、重大な意義を有するものです。
もっとも、本判決はそのような論拠でフェアユースを否定した事例ではなく、結論としてフェアユースを認めた上で一般論を述べたものにすぎません。実際に、著作権者が何をどの程度立証した場合に「市場の希釈化」によりフェアユースが否定されるのかは、今後の裁判例の蓄積を見守る必要があると考えられます。
また、わが国では、現在、著作権法30条の4ただし書きの解釈に関して次のような考え方が主流となっており(文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について」23頁(令和6年3月15日))、本判決とは異なり、AI生成物が学習された著作物と創作的表現において類似しないケースでは、たとえ「市場の希釈化」が生じているケースでも、著作権侵害が成立するとは限らない状況にあります。
著作権法が保護する利益でないアイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、特定のクリエイター又は著作物に対する需要が、AI生成物によって代替されてしまうような事態が生じることは想定しうるものの、当該生成物が学習元著作物の創作的表現と共通しない場合には、著作権法上の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。
もっとも、わが国ではこの点に関する裁判例がありません。
わが国の著作権法も、著作物の創作に対するインセンティブを確保することによって文化の発展に寄与することを目的の1つとする点では米国著作権法と共通しており、本判決の考え方も大いに参考になる部分があると思われます。
※この記事は、Yahoo!ニュース エキスパートに2025年7月21日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。
関真也法律事務所では、漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽・キャラクタービジネス・タレント・インフルエンサー等のエンタテインメント、ファッションのほか、生成AI、XR・メタバース、VTuber、デジタルツイン、空間コンピューティングその他の先端テクノロジーに関する法律問題について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。
こうしたクリエイターの法律問題に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。
《関連する弊所所属弁護士の著書》
《その他参考情報》
XR・メタバースの法律相談:弁護士・関真也の資料集