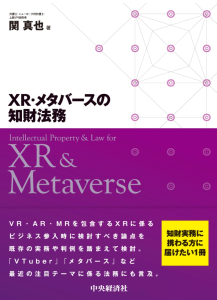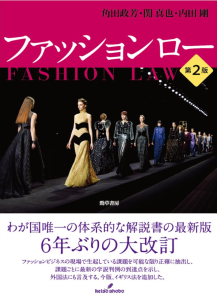ニューヨーク在住の声優である原告Paul Lehrman氏及びLinnea Sage氏が、『Genny』と呼ばれるAI音声ジェネレーターを提供する被告Lovo, Inc.(以下、Lovo社)に対し、『Genny』が原告らの声と同じ音を出力すること等につき著作権侵害を含む複数の理由に基づく主張をしていた事件において、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所は、2025年7月10日、著作権侵害を否定する内容を含む判決をしました(Lehrman v. Lovo, Inc., Case 1:24-cv-03770-JPO (S.D.N.Y. July, 10, 2025))。
Gennyモデルのアウトプット(すなわち、音声クローンそれ自体)に係る著作権侵害の主張につき、裁判所は次のように述べ、著作権侵害を否定しました。
著作権の保護は、この種の不完全な模倣には及ばない。これは、音楽のカバーやモノマネのような伝統的な技術ではなく、高度な技術を使用して達成された場合でも同様である。原告らが本質的に求めているのは、彼らの声そのものに対する著作権保護である。しかし、著作権は「アイデアの表現に及ぶものであって、アイデアそのものには及ばない」とされ(略)、「声」のような抽象的で無形のものには及ばない(略)。
米国著作権法上、音声は、「録音物(sound recording) 」というカテゴリーの「著作物」として保護を受けることになっています。この点、「実演」や「レコード」などの著作隣接権として保護もあり得るわが国の著作権法とは違った構造になっていることに注意を要します。
「録音物」とは、一連の音楽、会話その他の音声(映画その他の視聴覚著作物に伴う音声を除く。)を固定することによって得られる著作物をいい、ディスク、テープその他のレコード等録音物を収録する有体物の性質を問わない。
(米国著作権法101条より)
そして、この「録音物」の著作権者の排他的な権利は、「録音物に固定されている実際の音を直接又は間接に再録するレコード又はコピーの形式に、録音物を増製する権利」に限定され、「著作権のある録音物の音を模倣し又はそれに類似する音を含んでいたとしても、全体が他の音を独自に固定したものである他の録音物を作成し又は増製することには及ばない」とされています(米国著作権法114条(b))。録音物を模倣する新たな録音物は、たとえその模倣が極めて巧妙に行われているとしても、現実の複製がない限り著作権侵害にはならないとされているのです。
(※上記は「録音物」の著作権侵害に関する考え方であり、収録された音に係る台詞や歌詞、曲などの著作物に関する著作権侵害はまた別論です。)
ところが、本件において原告らは、Lovo社が、『Genny』を使用して、原告らのオリジナルの録音物の完全な複製物を生成したとは主張しておらず、むしろ、Gennyが「ピッチ、音量、トーン、音質、律動、抑揚、息遣い、粗さ、調子、ジッター(ピッチのバリエーション)、シャイマー(振幅のバリエーション)、スペクトル傾斜及び全体的な明瞭さ」など、原告らの声の属性を模倣した新しい録音物を作成することができると主張していました。
このため、たとえ原告らの声を固定した録音物を『Genny』のモデルの学習のために複製していたとしても、『Genny』の出力は、元の録音物の「増製」ではなく、これとは異なる新しい録音物を作成するものであるため、当該録音物に係る著作権を侵害しないと判断されたものと考えられます。
わが国著作権法のもとで考えた場合でも、声それ自体は表現ではなく、著作物として保護される対象ではないという点は同様であると考えられます。
しかしながら、わが国著作権法には著作権だけでなく著作隣接権があります。たとえば「実演家の権利」に含まれる録音権により、生成AIで声優本人の声を模倣した音を生成する行為を禁止するという方策を検討する余地があるでしょう。
ただ、統計的音声合成など、生成AIによる声の模倣の場合にどこまで実演家の権利が及ぶかについては、これを直接判断した裁判例は見当たらず、学説上も争いがある状況です。今後の裁判例を含む議論の進展を注視する必要があるでしょう。
なお、本件においては、アウトプットに係る著作権侵害以外の主張もされており、たとえば契約違反やパブリシティ権などの主張に関しては審理が続行されることになっているため、引き続き注目されます。
※この記事は、Yahoo!ニュース エキスパートに2025年7月22日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。
関真也法律事務所では、漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽・キャラクタービジネス・タレント・インフルエンサー等のエンタテインメント、ファッションのほか、生成AI、XR・メタバース、VTuber、デジタルツイン、空間コンピューティングその他の先端テクノロジーに関する法律問題について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。
こうしたクリエイターの法律問題に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。
《関連する弊所所属弁護士の著書》
《その他参考情報》
XR・メタバースの法律相談:弁護士・関真也の資料集