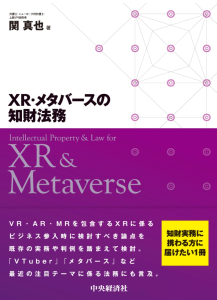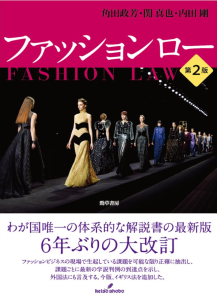はじめに
令和7(2025)年4月3日、産業構造審議会知的財産分科会第18回意匠制度小委員会が開催され、「仮想空間におけるデザインに関する意匠制度の在り方」などについて議論が交わされました。
同年2月10日に開催された第17回意匠制度小委員会の議論を受け、主に以下の2点について検討されました。
①意匠制度の見直しの必要性
②意匠制度見直しを行う場合の制度的措置の方向性
上記②については、とりわけ、第17回で事務局から提案された「方向性③」に対する賛否について意見が交わされました。
【方向性③の概要】
・操作画像・表示画像に該当しない画像であっても、物品等の形状等を表した画像であれば、画像の意匠として保護の対象とする。
・物品等の形状等を表した画像の意匠権の効力は、同一又は類似の画像の意匠に及ぶ(物品等の意匠には及ばない)。
第17回のレポートはこちら。
仮想空間における意匠保護、特許庁で議論進む~現実とメタバースで問われるデザイン保護制度の設計~(関真也) – エキスパート – Yahoo!ニュース
意匠制度の見直しの必要性について
今回の議論で表れた限り、仮想空間におけるデザインの模倣に対応するために意匠制度の見直しを行う必要性はあるという点で、委員の意見は概ね一致していたようです。
その背景には、メタバース市場が拡大する見込みがある中、仮想空間において利用可能な3Dモデルを販売するプラットフォームやゲームをメインコンテンツとする仮想空間プラットフォームを中心に、国内外を問わず模倣事例が発生しているところ、著作権法や不正競争防止法による法的対応が困難な場合があるとの指摘があります。
著作権法では、実用品や建築物のデザインの保護を狭く解釈する裁判例の傾向にあるため、現実の物品等の形状等を表わした画像の保護も否定される場合が多いのではないかという意見があります。
また、不正競争防止法2条1項3号は、3D画像の形態が保護対象になると解されているものの、実質的に同一のデザインのみが規制される点、保護期間が国内販売開始から3年に限られる点などにおいて保護が狭く、対応し切れないケースがあるのではないかという意見があります。
こうした状況にあることから、今回の議論においても、仮想空間においてもデザインが保護されるという明確な法的根拠が必要であるという意見が多く聞かれました。
3D画像のデザインが意匠法の保護対象となれば、権利の有無や内容等は意匠登録のデータベースによって確認でき、登録されている意匠は特許庁の審査も経たという信頼性があるため、模倣があった場合に、プラットフォームから削除等の協力を得やすいというポジティブな側面もあります。プラットフォームにとっても、権利侵害のない3Dモデルを不用意に削除すると、その3D画像を利用・販売等するユーザーからクレームを受けるおそれがあるため、権利の存否等を確認しやすい制度となることは好ましい面があるといえそうです。
意匠制度見直しの方向性と課題
見直しの方向性③は、特許庁が事業者等に対して事前に実施したヒアリングにおいても、ユーザーニーズに見合ったバランスの良い案であるとの評価をうけているとのことです。また、今回の議論においても、方向性③に賛同するとの委員の意見も複数みられました。
他方で、いくつかの懸念も残されています。
意匠権は、著作権法や不正競争防止法2条1項3号と異なり、依拠性を侵害要件としません。つまり、登録意匠の存在を知らずに創作したデザインが、たまたま登録意匠と類似していた場合でも、意匠権侵害は成立し、差止請求、損害賠償請求等の対象となる可能性があります。
このため、物品等の形状等を模した3D画像が新たに意匠法の保護対象となった場合、3D画像を制作、利用、販売等するクリエイターや企業は、意匠権侵害となるリスクを予防するために、他者が先行して類似する意匠を登録していないかを調査(クリアランス調査)する必要が生じることになります。他者のデザインを参考にせず、自らのクリエイティビティを発揮して独自に作り上げたものだから大丈夫、というわけにはいかなくなるわけです。
また、このクリアランス調査の負担があることに加え、他者の先行登録意匠と偶然に類似してしまった場合でも意匠権侵害となることなどから、3D画像を制作するクリエイターに対して萎縮効果が生じないかという懸念も指摘されるところです。
とりわけ、個人クリエイターやスタートアップなどにとっては、自らは費用をかけて万全の意匠登録を備えることが困難な場合がある一方、上記のようなクリアランス調査の負担を強いられることとなり得ます。これでは、かえって創作活動に支障を生じ、仮想空間ビジネスの発展にとって好ましくないかもしれません。
これらのことから、今回の議論では、意匠制度の見直しにあたっては、クリアランス調査の負担を軽減するための対応策を整備する必要があることが繰り返し指摘されました。たとえば、①どのような画像が新たに保護対象となるのか、②どのような行為が意匠権侵害になるのか、③どのような要素を考慮して意匠の類似性が判断されるのか、そして④効率的な調査環境の整備等について検討する必要があるとされています。
※この記事は、Yahoo!ニュース エキスパートに2025年4月5日付けで掲載した記事を一部更新し、転載したものです。
関真也法律事務所では、漫画・アニメ・映画・TV・ゲーム・音楽・キャラクタービジネス・タレント・インフルエンサー等のエンタテインメント、ファッションのほか、XR・メタバース、VTuber、デジタルツイン、空間コンピューティング、生成AIその他の先端テクノロジーに関する法律問題について知識・経験・ネットワークを有する弁護士が対応いたします。
こうしたクリエイターの法律問題に関するご相談は、当ウェブサイトのフォームよりお問い合わせ下さい。
《関連する弊所所属弁護士の著書》
《その他参考情報》
XR・メタバースの法律相談:弁護士・関真也の資料集